B’AI グローバル・フォーラムを拠点として活動する産学共同研究グループ「メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)」は2021年12月5日(日)、「衆議院選挙報道とジェンダー表現を考える」というテーマで非公開のオンラインワークショップを開催した。
2021 年 10 月 31 日に行われた第 49 回衆議院議員総選挙。2018 年に「政治分野における男女共同参画推進法」が成立し、2021年には「ジェンダー平等」が流行語大賞のTop10入りするほどジェンダーの問題が社会課題として大きく浮上したが、それにもかかわらず今回の衆院選は当選者の女性比率が9.7%と改選前を下回る残念な結果となった。このような結果を受けて、本ワークショップでは、日本の政治の場で女性が増えない理由を選挙報道の課題と関連付けながら検討し、今後ジェンダー格差の改善に向けてメディアにできることは何かについて議論を行った。ワークショップにはMeDiとB’AI グローバル・フォーラムのメンバーの他、報道の現場でジェンダー課題に取り組んでいるおよそ30人のメディア実務者が参加し、MeDiメンバーの小島慶子氏(エッセイスト)がファシリテーターを務めた。
- 日時:2021年12月5日(日)13:00-15:00
- 形式:オンライン
- 参加者:46人(MeDiメンバー、B’AIメンバー、メディア関係者)
冒頭の開会挨拶でMeDi座長の林香里教授(東京大学大学院情報学環、東京大学副学長、B’AIグローバル・フォーラムディレクター)は、今回のワークショップのテーマとして選挙を選んだ理由について、様々な政治報道の中でも最もダイバーシティが欠けているのが選挙報道であるという点を挙げ、現状のままでは選挙報道というものがますます私たちの日常から離れてしまい投票率の低迷にもつながりかねないとの懸念を示した。いかに選挙報道に幅を持たせることができるか、また政治の場でジェンダーバランスを確保するためにメディアはどのように貢献できるか。これらの質問について、参加者で議論するに先立ち、政治とジェンダーの関係を専門とする上智大学法学部の三浦まり教授にご講演をいただいた。
上智大学・三浦まり教授の講演「総選挙報道とジェンダー」
三浦教授はまず最初に、報道において女性政治家がどのように表象されることが多いのかについて、政治報道が日本よりジェンダー化されているアメリカの研究を紹介した。それによると、アメリカの報道では、女性政治家の場合、男性と比べて私生活や容姿、感情を吐露する場面に焦点が当てられる傾向が強く、自身の能力よりも父親や夫など有力な男性との関係が強調されがちで、声については否定的にコメントされる(高いとリーダーに相応しくないということで、逆に低いと男性の真似をするということで)ことが多いという特色がある1。このような表象の結果、女性は感情的であり、政治家としての能力より見た目の方が重要で、リーダーには向いていないというメッセージが作り出されるということである。また、政治家だけでなく企業の経営者なども含め、権力的な地位にある女性が報道の中でどのように扱われるかを分析した別の研究もあり、そこでは女性の描き方として「性的な存在、母親、飾り、 鉄の女」という4つのステレオタイプが指摘されているという2。
次に、ジェンダー問題の扱いという観点から三浦教授は日本の最近の選挙報道を振り返られた。教授によると、2018 年の「政治分野における男女共同参画推進法」成立以降、女性議員の少なさや女性が抱える障壁について取り上げる報道はかなり増えている。しかし依然として課題は多く、例えば女性候補者・議員が増えない理由について最も説明責任が問われるはずの各政党に対し、メディアが責任追及の役割を十分に果たしたかについては検証が必要であると指摘した。また選挙報道にダイバーシティがない要因の一つでもある選挙制度の構造的な問題についてももっと取り上げなければならないと付け加えた。
これらの内容を踏まえて今回の総選挙がどうだったかを見てみると、まず目立つのは有権者によるSNS上での投票呼びかけがとても増えたこととその影響で政策争点が多様化したことが挙げられると三浦教授は説明する。そうした中で、ジェンダー平等はちゃんと争点になっていたかというと、マスメディアの縦割り組織を背景に、社会部などが普段報じていた「コロナ禍の女性への打撃」のようなジェンダー関連問題が政治部の選挙報道とつながらず結局前景化しなかった側面があったという。一方で、それなりにジェンダーの争点を取り上げていた立憲民主党や日本共産党が議席数を減らしたということで、「ジェンダーの話はやはり票にならない」というシニカルな見方が浮上したが、これについて三浦教授は、日本の場合小選挙区という構造的な理由などによってそもそも政策を争点とする選挙戦になりにくいのが背景にあると指摘する。小選挙区になって明らかに投票率が下がっており、そのような構造の中では争点が多様化したといっても結果を支配するのは依然として「政党支持」と「経済」の2つであるが、だからこそメディアの役割が重要で、全体の構造を変えていくためには小選挙区の特色を意識した報道や一票の価値を実感させるような報道がもっと必要であると強調した。
ーーー
1 https://theconversation.com/five-ways-the-media-hurts-female-politicians-and-how-journalists-everywhere-can-do-better-70771
2 Carlin, D.B. and K. L. Winfrey. 2009. “Have you come a long way baby? Hillary Clinton, Sarah Palin, and sexism in the 2008 campaign coverage.” Communication Studies 60: 326-343.
実務者からの問題提起
続いて、MeDiメンバーの山本恵子氏(NHK名古屋拠点放送局報道部副部長)と浜田敬子氏(ジャーナリスト)が、実務者の観点から選挙報道とジェンダーの問題についての論点を整理した。
第一の論点として挙げられたのは「公平・中立な報道」の限界についてだった。公平・中立とはこれまでマスメディアの選挙報道において大原則とされてきたが、今回よく言われていたのは、「公平・中立な報道」を意識するあまり当たり障りのない報道しかされず、特にテレビの場合は報道量自体が少なかったのではないかということであった。その結果、争点などを掘り下げて分析するというところまではできず、本当に有権者に参考になるような情報が発信できたかについて問題意識を持っていると山本氏は語った。
次に、「ジェンダー争点化の実践と課題」について浜田氏は、近年の選挙では候補者や政党へのアンケートの中に「選択的夫婦別姓」や「同性婚」などシンボリックな質問が入っていてその面ではジェンダーが争点化してきた感じがするが、一方で、例えばコロナ禍における女性の困窮や社会保障制度など大きな社会構造との関連でジェンダーを争点化していたかというとまだまだ足りないところが多いと指摘した。
最後に、「今後の選挙報道の課題」については、有権者の関心を高め、かつ女性議員を増やしていくためにも、選挙の前後だけでなく普段からジェンダーなどの争点について発信し続けることが大事であるということでまとめられた。
ブレイクアウトセッションでの議論
全体セッションの後は、40分間のブレイクアウトセッションが設けられた。6-7人で1つのグループとなり、全部で8グループがそれぞれ持ち寄った記事や番組の事例を材料に今回の選挙報道における問題点と今後の改善策について意見を交わした。
各グループで議論された内容をまとめると、共通して話題に挙がったのは、報道現場で感じたジェンダー問題を取り上げることの難しさだった。新聞やテレビのようにマスに向けて情報を発信するメディアの場合、限られた枠の中でジェンダーという話題をどこまで特化して伝えられるかといった時に様々な要因が壁となるということである。その要因の一つとして挙げられたのが、実務者からの問題提起にもあった「公平・中立な報道」の原則である。この原則の下ではどうしても政党間の出演者数や露出時間など量的な公平性が優先されるため、争点となる社会問題に踏み込んでニュースにするのがなかなか難しく、その中でも特にジェンダー問題は後回しにされやすいという。というのも、ジェンダーの話題を取り上げようとすることへのバックラッシュが社内に実際存在するということで、「ジェンダーの話は緊急性がない」「余裕のある人の話題」「数字が取れない」などの反応にしばしば直面するという悩みが共有され、意思決定層をはじめメディア組織内のダイバーシティへの認識がいかに不十分なのかが窺えた。
一方で、選挙報道にダイバーシティを持たせにくいもう一つの構造的な要因として「縦割り組織」というキーワードが頻繁に登場した。例えば、ジェンダーの問題とは単体として存在するのではなく様々な社会問題とつながっているので、政治部と社会部が連携することでジェンダーを含めてより多様な争点に目を向けることもできるはずだが、実際は報道局の中で政治部の地位が非常に高く縄張り意識も強いため、政治部から情報を共有してもらうことも選挙報道に他部署が関与することもなかなか難しいという。さらに、最近の若者の関心事にはジェンダーに限らずアニマルライツや気候変動など、政治・経済・社会を横断する多様なテーマが多いが、そういうところにも縦割りの閉鎖的な構造ではうまく対応できないという側面があり、若年層の政治参加を促すためにも縦割りの問題は変えていかなければならないという問題提起がなされた。
これらの限界を踏まえた上で、今後の選挙報道のためにどのような取り組みが必要なのかについてまとめると、まず、「公平・中立な報道」の原則がもたらす困難への対策として、発信方法の多様化という観点からデジタルを積極的に活用するという案が提示された。デジタルには尺や紙面の制限がなく、さらに縦割り構造の縛りも比較的緩いので、そのような強みを活かせば社会問題と各政党の政策や争点をちゃんと結び付けた上で面白くて分かりやすい情報発信ができるのではないかという意見であった。
また、有権者に必要な情報をしっかり伝えるという観点では、報道の期間というのを見直す必要があるとの指摘も出た。選挙期間はとても短いのでその期間だけでは十分な情報を提供できないし、例えば女性議員が増えない理由などについては候補者が決まっている段階で取り上げてもあまり意味がない。そのため、そのような問題提起をより有効に行うために、選挙報道という括りではなくて政治報道という括りで中長期的に取り組んでいくことが重要ということである。そうすることで、公示前、つまり「公平・中立な報道」の縛りが厳しくなる前に様々な伝え方を試みることができるし、選挙が終わった後も各有権者の投票行動に影響した要因についてしっかり分析するような報道ができるだろう。
最後に、全体的な議論は主に選挙報道においてジェンダーを取り上げることの難しさを中心に進められたが、実際は過去と比べると最近では報道量も増えつつあり閲覧数や視聴率も伸びているということなので、そこは前向きに評価しなければならない。ただ、メディア内部には依然として「ジェンダーは数字が取れない」という考えを持ち続けている人が多いので、エビデンスに基づいてその感覚的なズレを払拭し、社内でまずジェンダーというテーマを正しく評価することが重要であると指摘された。もちろん大前提として、「数字を取れる/取れない」ではなくこれがいかに大事な問題なのかを発信する側がしっかり認識しなければならないということはいうまでもない。
ここまでの各グループの発表を受けて、ワークショップの最後は三浦教授の感想で締め括られた。報道現場でジェンダー課題に取り組んでいる方々の話からやはりバックラッシュが起きているということを改めて実感したという三浦教授は、バックラッシュとの戦い方の一つとして、一人ひとりの生きづらさを伝える際に、その生きづらさを作り出している制度にもしっかり目を向け、さらにジェンダーを横串として刺していくという伝え方があり得るだろうと述べた。そして、なぜ女性議員を増やさなければならないのかという根本的な話にどのようにもっと説得力を持たせられるかという参加者の悩みに対し三浦教授は、その議論は女性だけでなく男性にもメリットがあるといういわゆるメリット論になりがちだが、そのようなフレームで話が進んではならない、ジェンダー平等というのはメリットの問題ではなく、人権の問題であり民主主義の問題であるということを伝える側がまずしっかり認識しなければならないのである、と強調された。
報告者:金 佳榮(東京大学大学院情報学環 特任研究員)
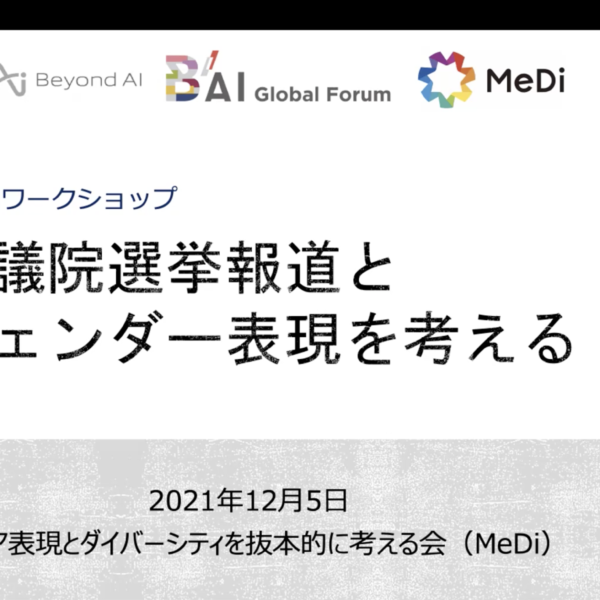
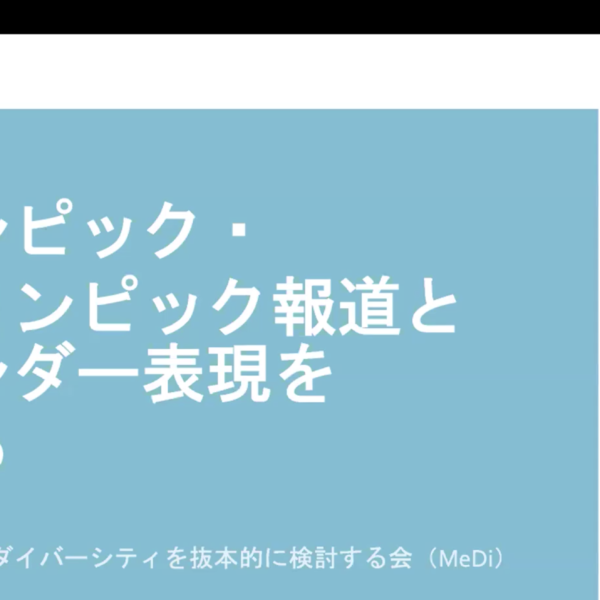

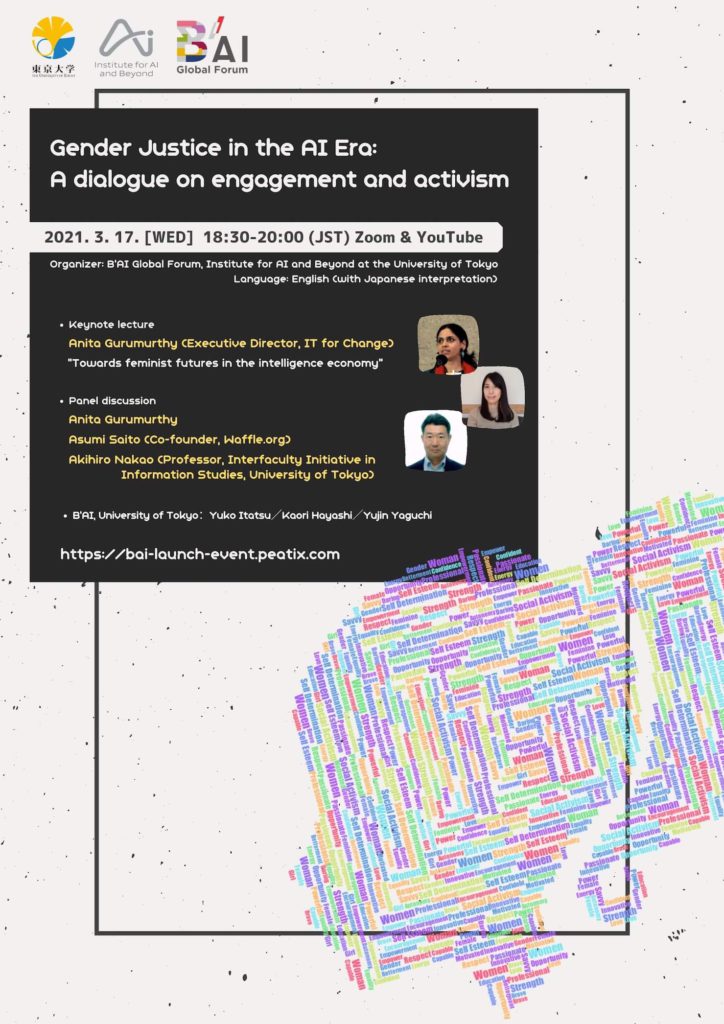










-600x600.jpg)






